知識の幅について、気にしたことはありますか?
本書によると特定の分野の専門家/スペシャリストもいいけど、知識の幅やゼネラリストも、成功できる事例があり推奨されています。
単純で決まりきった環境ならいいけど、現代のように複雑で不確実性が高い環境において幅広い知識が役立ついうことが事例を交えて説明されています。
幅広い分野にまたがる知識や、経験したりすることが重要ってことなのですね。
また、この本は人生の回り道、寄り道をしてきた人たちを勇気づけるものです。
- RANGE(レンジ) 知識の「幅」が最強の武器になる (デイビッド・エプスタイン 著)について感想と書評です。
- 本書を読むメリット
- 知識の幅がどのような役に立っているのか実例を交えて知ることが出来る。
- 早期の専門特化がもてはやされ、さまざまな分野での経験は軽視されている。それらに一石を投じる内容となっている。
- こんな方におすすめ
- 自己成長したい方(学業、音楽、スポーツなど)
- 知識の幅の活用事例について知りたい方(専門特化との比較)
- 学業やスポーツの教育にご興味のある方
概要
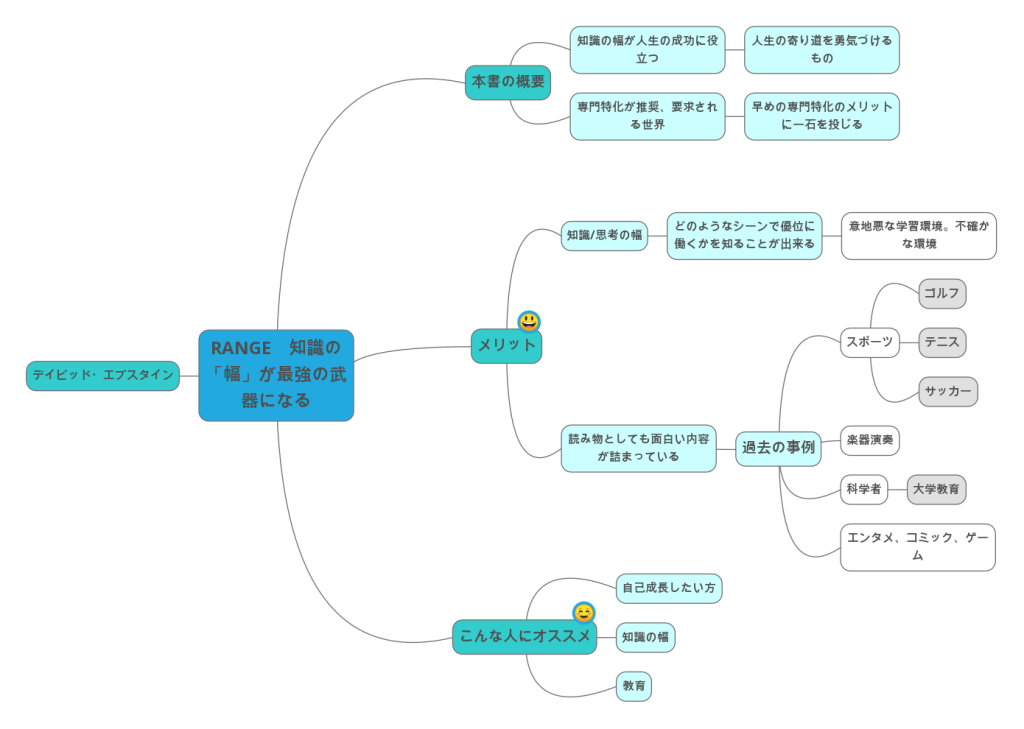
みなさん、こんにちは! Nくまです。
今回は、デイビッド・エプスタインさんの
RANGE(レンジ) 知識の「幅」が最強の武器
について紹介・感想を書かせていただきます。
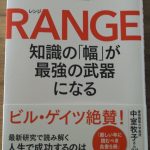
タイトルの通りなのですが、あまり注目されていない知識の幅(RANGE)について、いくつかの成功事例をもとに紐解かれています。
スポーツの場面でも様々なスポーツを体験することのメリットがあることや(ロジャー・フェデラーに注目されています)、
学業では専門分野をいくつも経験することが、いろんな分野での応用がしやすいなどです。
個人的に自分の人生を振り返ってみると、人生の役に立ったのかよくわからない寄り道・回り道をしていた時期もあったりして、人生に回り道ってなんだか失敗した感じがしますよね。
しかし、そんな人生においての無駄そうな時間や、人生の回り道が案外役に立つという話が本書で取り上げられておりました。
これまでの印象が変わるかもしれません。

かくいう私は、人生の回り道をしているときがあった(大学での研究期間が長かった)。後ろめたい感じもありましたが、この本から勇気をもらいました
本書を読むキッカケ
メンタリスト DaiGo さんが YouTube動画でこの本を紹介されていました。
読書好きの DaiGo さんがオススメされる本について、自分は気になってしまう性分であります。
概要はこの本のタイトル通りなのですが、そういえばこういう知識の幅についての本はほとんど読んだことがなかったので興味を持ったことと
自分の普段の仕事においても、様々な分野によって構成されているため、知識の幅がある人、横断的に考えられる人じゃないと解けない問題ってのを感じます。
現実的にはどうなんだっていうと、そういうことを出来る人はほとんど居ないし、自分たちの分野に固執してしまっていることを感じます。
そういう日常の閉塞感もありましたので、何かしらヒントを貰いところもありました。
また、自己成長にもつなげていきたいところも興味がありましたので、本書を手に取りました。
本書からの気づき
本書は、いろいろな人生のヒントが詰まっていて、内容が面白いのですが、いくつか気づきを書いてみます。
デメリット
本書のデメリットは次の通り
- 約400ページとボリュームが多い。
- イラストは少なくて直感的に分かりにくい。
自分にとっては時間がかかってしまい読むのに数日かかってしまいました。
人によっては読みづらさを感じるかもしれません。
メリット
一方で、本書のメリットは以下の通り。
- 読み応えのある本になっており、面白いエピーソードが詰まっている。
- 人生の成功、能力を伸ばす知識獲得について、人生のヒントが書かれている。
- 知識の幅が広いことによるメリット
- 実例や調査結果を交えて紹介されているため、説得力がある。
- 過去の成功例の紹介
ボリュームがある一方で、過去の成功例を紐解いて、知識や思考の幅がどのように活用され成功に結びついたのか知ることが出来ます。
具体的にどういうこと? 例えば 優秀な科学者

いまの自分自身に近いところで考えてしまったのですが、科学者で比較するだけでも、違う別分野を知っているかどうかで、優秀さが変わってくるような内容がありました。
以下は本書からの引用です。
(優秀な科学者)
科学者と一般の人たちでは、芸術的な趣味を持っている度合いはそう変わらないと思われるが、最高レベルのアカデミックな科学者は、本職以外に本格的な趣味や副業を持っている可能性がはるかに高い。さらにノーベル賞を受賞した人たちでは、アマチュアの俳優やダンサー、マジシャンなどのパフォーマーである確率が少なくとも22倍高い。
また、全国的に知られている科学者は、他の科学者と比較して、音楽や彫刻、絵画、版画、木工、機械工作、電子機器いじり、ガラス細工、詩作などをたしなんでいる可能性がずっと高く、フィクションやノンフィクションを執筆している可能性もはるかに高い。ノーベル賞受賞者になると、さらにその確率は上がる。
RANGE 第1章 早期教育に意味はあるか
つまり、本業とは別の分野の趣味や副業があることで、よりよい仕事が出来るということです。
また、これは一例ですが、これと似たような内容、知識の幅が役に立っている事例が他の分野でも見られます。
スポーツ、音楽、仕事・・・
こういうのを聞くと、異なる分野についても興味を持って取り組んだほうがいいってことですね!
今後の活動に活かすこと

実際、今後の活動に活かすとなると、自分の知識の幅を増やしていきたいですね。
そうなると、以下のことを始めてみます!
個人的に難しいところはありますが、本業とは別の趣味を持つことの重要性を感じました。
科学者のところにあった芸術的なところからでも、いいのかも知れませんね。
皆様も、全然別のことをやってみるのもいいかもしれません。
まとめ
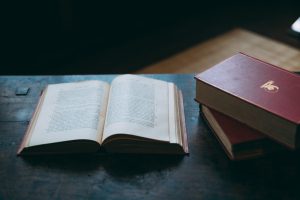
本書を通じて、幅広い知識/経験のメリットを知ることが出来ます。
メリットを知った後、それら(多様性)を得たいと思ってしまうことと、自分の棚卸しを通じて、他に興味を持てるものがないか、自分にマッチしているものがないか探す旅に出るのもいいかも知れません。
それを通じて人生や仕事に活かせるところあるかもしれません。
自分の方でも、ソフトウェアだけではなく、電子回路についても多少分かっているところがあるため、そういうところで役に立っているところはあります。
ちょっとずつでも隣の分野のことを知ることも大事だと思いますね。
また、何気に小説は好きですし、学生の頃はよく読んでました。
そういうところも、無意識に役に立っているんじゃないかと思えてきました。
ご興味がわきましたら、ぜひ、本書を手にとって読んでみてください。
追伸(一考)
自分の経験を振り返ると高校生や大学生のとき、理系か文系か選ばされたり、大学を選ぶ際も入学する分野・学科を決めないといけなかったりとありました。
本書によりますと、大学の授業も専門化されすぎて、隣の分野に全然明るくないという話がありましたね。
こういうことを聞くと、自分が大学生の時を振り返ってしまうのですが、たしかにそういうところがあったと思います。
一方で、大学生の時の友達やサークル活動、遊び、マージャン、ゲームを通じて得たものが案外とその後の役に立っているところがあります。
そう考えると単に学業だけではなく、遊びから得たものとか、ゲームや読書を通じて得た幅広い知識といっていいのか、微妙なことも役に立っているのかもしれませんね。
あとは、内容とは全然関係ないのですが、ブール代数のブールはイギリスの論理学者の名前だったんですね。知りませんでした(普段よく使っているのに…)。
それをシャノンさんがうまく組み合わせたって情報を符号化したとありました。それもすごいですね。ちゃんと理解できていませんでした・・・
そういうパソコンとかブログとかインターネットとか、そういう様々な功績から出来ているのですね。感謝感謝
この本は少々難しいところがありますが、読み応えがある面白い本なので、また読み返してみようかと思います。
関連記事
メンタリストDaiGoさん関連記事です。
よろしければどうぞ
知識の幅のメリットについては、この多様性の科学にも通じるところがありますね。
それではまた🐧





コメント