先日の新聞で架空請求詐欺、サポート詐欺が増えているという記事がありました。
こういう不当な請求があったとき、みなさまどうされてますか?
ドキッと感じてしまうかもしれませんが、そんなときでも冷静に対処して、お金を払わないように気をつけましょう!
急に迫られると正常な判断ができなくなってしまいますので、少し落ちつくことと、身近な人に相談することをオススメします。
不安なときや被害への相談は最寄りの警察署または県警本部に相談してください。
架空請求やフィッシング詐欺に騙されないコツ

さっそくですが、私なりの結論を書きます。
即断即決しない
前頭葉を鍛える(メタ認知)
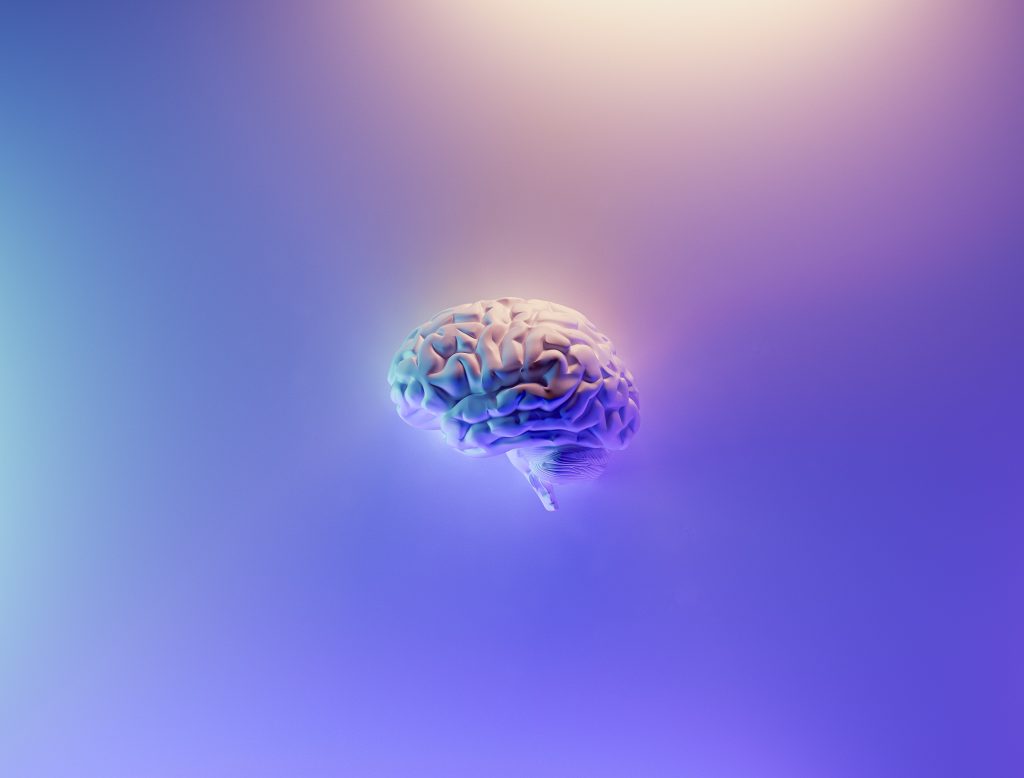
前頭葉は冷静な判断をするために欠かせません。
様々な本で述べられておりますが、前頭葉を鍛えるためにはマインドフルネス、瞑想がオススメです。
呼吸を整えるだけでも効果はありますので、日々の生活に取り入れられてはいかがでしょうか。
つまり、本能(大脳辺縁系)ではなく理性(前頭葉)を起動することで、慌てず冷静な判断をできるようにするという考えです。
他のキーワードとして「メタ認知」という言葉もあります。
自分自身の感じ方・考え方を客観的にとらえる能力のことで、これがあることによって冷静に自分自身の行動を考え直す、疑うことができるはずです。これに繋がってくる話になります。
知識を身につける

詐欺行為について知る、知識を増やすことも効果的です。
警察のメール配信に登録
お住まいの県、府、都、道の警察から情報発信されているメールがあります。
(福島県ですと「POLICEメールふくしま」というのがあります。場所によって名前は違うようです)
こういうメールに登録しておくことで、どのような事件、事故があったかなど、日々送られてくるようになります。
最近はどのような詐欺被害があったか、どういう手口が多いのか知ることができます。
防犯になりますのでオススメです。
また、怪しい電話や詐欺があった場合、情報提供しやすくなりますね。
関連書籍を読む
ロバート・B・チャルディーニ氏の
「影響力の武器」
が非常に参考になります。
こちらはメンタリストDaiGo氏もオススメしている本です。
少々分厚いですが、騙されやすい人は必読の書です。
騙されやすい著者Rチャルディーニ氏が、心理学的にどのようなことが起こっているかまとめている本です。
今回の内容に近いのは「希少性」です。
時間限定、地域限定そういったものに価値を見出してしまう心理です。
急かされると冷静な判断ができませんし、なおかつ「今すぐに」〇〇してもらえれば、●●というメリットが・・・
と言われると通常より重要なものと感じちゃいますよね。
締め切りが近いと(内容はどうであれ)それだけで人は重要なものと考えてしまいます。
これはよくある詐欺の手法なので、それを知るだけでも勉強になります。
オレオレ詐欺のことを知る
オレオレ詐欺についての本もあります。
自分はこの本だけ拝読させてもらいましたが、想像以上に組織活動になっており立派な企業を連想させられます。
それぞれの役割をこなしていったり、詐欺市場に生きる人々のことについて書かれていて興味深いです。
調べたり相談する

例えば送られた文面をコピーしてGoogle検索すると、同じ境遇の方の情報がヒットすることがあります。その情報があるだけでも心強いですよね。
また、身近な家族や友人に相談するだけでも効果はあります。
警察でも相談を受け付けております。
その新聞によると最寄りの警察署、県警本部に連絡すると相談にのってもらえます。
(あまり無いはずですけど)請求が正当なものなのか、確認できるのかもしれません。
おまけ:ChatGPT
おまけとして、騙されないコツをChatGPTに聞いてみました。
以下は、ChatGPTによって提供された内容になります。
架空請求詐欺とフィッシング詐欺は異なる手法ですが、いくつかの共通する見分け方があります。以下は、どちらの詐欺にも当てはまる可能性があるポイントです。
- リンクの確認:
- どちらの詐欺でも、不審なリンクを含むメッセージやメールには注意が必要です。
- リンクをクリックする前に、そのURLを確認して、信頼できるものかどうかを確認しましょう(組織・会社名や国コードなど)
- 急な支払い要求に注意:
- 詐欺師は被害者を焦らせ、急な支払いを要求することがあります。冷静に判断し、不審な請求や要求に対しては慎重になりましょう。
- 文面の確認:
- 脅迫的な文言や不自然な表現は、どちらの詐欺でも共通しています。急な行動や情報提供を求めるメッセージには注意が必要です。
- 連絡先の確認:
- 請求書やメッセージに記載された連絡先が不審であれば、公式な手段で連絡をとることが大切です。
- メッセージ内の連絡先ではなく、公式なウェブサイトや公式な連絡手段を利用して確認しましょう。
- 二段階認証の利用:
- オンラインアカウントには可能であれば二段階認証を使用しましょう。これにより、不正アクセスを防ぐことができます。
- 冷静な判断:
- 脅威や緊急性を感じさせるメッセージに対しても冷静な判断を心がけましょう。焦らされず、慎重に行動することが重要です。
これらの共通するポイントを覚えておくと、架空請求詐欺やフィッシング詐欺から身を守るのに役立ちます。冷静な対応と情報の確認が詐欺からの防御につながります。
代表的な詐欺の例

パソコンやスマートフォンを通じて行われている代表的な詐欺についてChatGPTに列挙してもらいました。
以下は、「ChatGPTによって提供された内容」です。
- フィッシング詐欺:
- 被害者になりすまして、偽のウェブサイトやメールを通じて個人情報やアカウント情報を詐取する手法。銀行やオンラインアカウントに関連することが多い。
- 架空請求詐欺:
- 存在しない商品やサービスに対する請求を装い、被害者からお金をだまし取る手法。
- ランサムウェア:
- コンピュータ内のファイルやデータを暗号化し、被害者に身代金の支払いを要求する手法。身代金を払わないとデータが解放されないことが脅迫される。
- サポート詐欺:
- 偽の技術サポート担当者が被害者に連絡し、存在しないウイルスや問題を装い、高額なサポート料金をだまし取る手法。
- 投資詐欺:
- 被害者に高いリターンを約束して、架空の投資機会や会社に投資させ、その後投資金を奪う手法。
- 偽のチャリティ詐欺:
- 偽の慈善団体や支援活動を装い、寄付を募り、その資金を詐取する手法。
- ウイルス感染の警告詐欺:
- インターネットブラウジング中にウイルス感染の警告を出し、偽の技術サポートに電話するよう促し、高額なサポート料金をだまし取る手法。
- 賞金や景品詐欺:
- 偽の賞品や景品を約束して、個人情報や送金を詐取する手法。
これらの詐欺から身を守るためには、冷静な判断、正規の連絡手段の利用、セキュリティ対策の強化が重要です。急な要求や不審なメッセージには慎重に対応し、定期的なセキュリティのアップデートや情報の確認を心がけましょう。
考察
このように、様々な詐欺の手法があるわけですね。
これら一つ一つを覚えていくことは大変です。
そんな中で、冒頭で申し上げましたが色々なことに応用できる対処法を身につけておくだけで役に立ちます。
手軽なところとしては、警察メールに登録しておくということでしょうか。
こういう事件や事故の情報はありがたいものなので是非利用しましょう。
また、冷静な判断というは、何が起こるかわからない世界で特に有効です。
普段からマインドフルネスや瞑想で練習しておけば大きな武器になることでしょう。
まとめ

架空請求詐欺、フィッシング詐欺で騙されないためのコツについて私なりに考えていることを書いてみました。
こういうデジタル技術は人類の歴史でもまだ日が浅く、なかなか慣れない方が多いのが現実なのかもしれません。
巧妙な手口で、あの手この手とやってきますので、気をつけてまいりましょう。
今回はお友達からの情報提供から作成した記事になります。
情報提供に感謝するとともに、みなさまのなにかの参考になることをお祈りします。
あとがき


(自分のスタンドFMから)
正直なところ私は新聞を読まないので全然知らなかったんですけど、 県内でサポート詐欺が増えているってお話でした。
ちょうどその方のお父さんですね、60代ぐらいだと思うんですけど、 似たようなことがあって表示された番号に電話しちゃったって言うんですね。 そういう事例が身近にあったわけなんです。みなさんは下手に電話したらだめですよ。
実際サポート詐欺って私知らなかったんですけど、 自分が受信しているメールにですね、 ポリスメール福島ってのがありまして、ほぼどの県にも県警さんから出てるメールってあると思うんですよね。
これは自分が町内会の役員をやってて知ってたんですけど、 そのポリスメールってやつによくサポート詐欺って回ってたんですね。
まあどちらかというとクマの目撃が多すぎて埋もれるんですけど。
ちなみに その新聞を見てですね、少しだけサポート詐欺の内容がわかったんですけど、 パソコンを使っててインターネットで閲覧中にウイルスに感染したって警告画面が出るみたいです。 そこで表示された連絡先に電話すると、サポート料というか復旧料の名目で電子マネーの購入を求められるという、そういうお話みたいですね。
そういう詐欺があることをまず知っておくのが一つ必要なのかもしれませんね。
どうやったら見分け入れるの?みたいなことを私に聞いてるんだと思うんですけど、それはちょっと一概に言えないんですが、 まずは知るところから始めてみるのがよいです。
その次にですね、一旦冷静になることが大事だと思うんです。
周りの家族とか、詳しい友人とかですね、相談してみるのがいいですね。
そういう方がいらっしゃらなくても、最寄りの警察署とか、 県警本部に相談もできるようなことを新聞に書かれてたので、そういう不審なものとかに対しては、相談してみるというのはありかもしれませんね。
関連記事
先述しましたが、他人に騙されないために読むべき本です。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
それではまた🐧


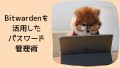

コメント